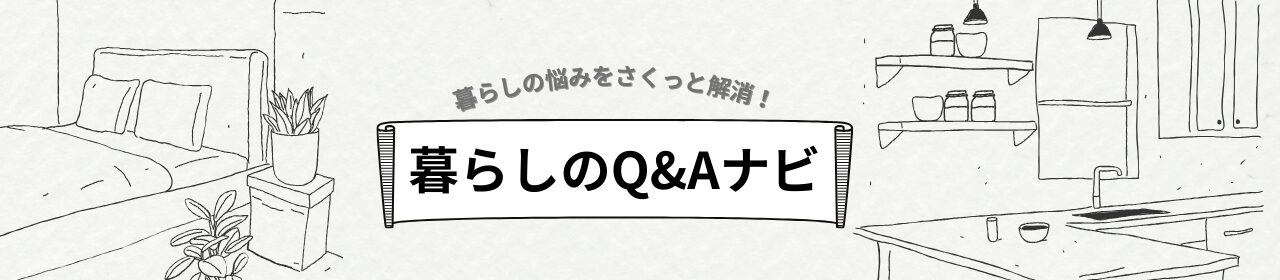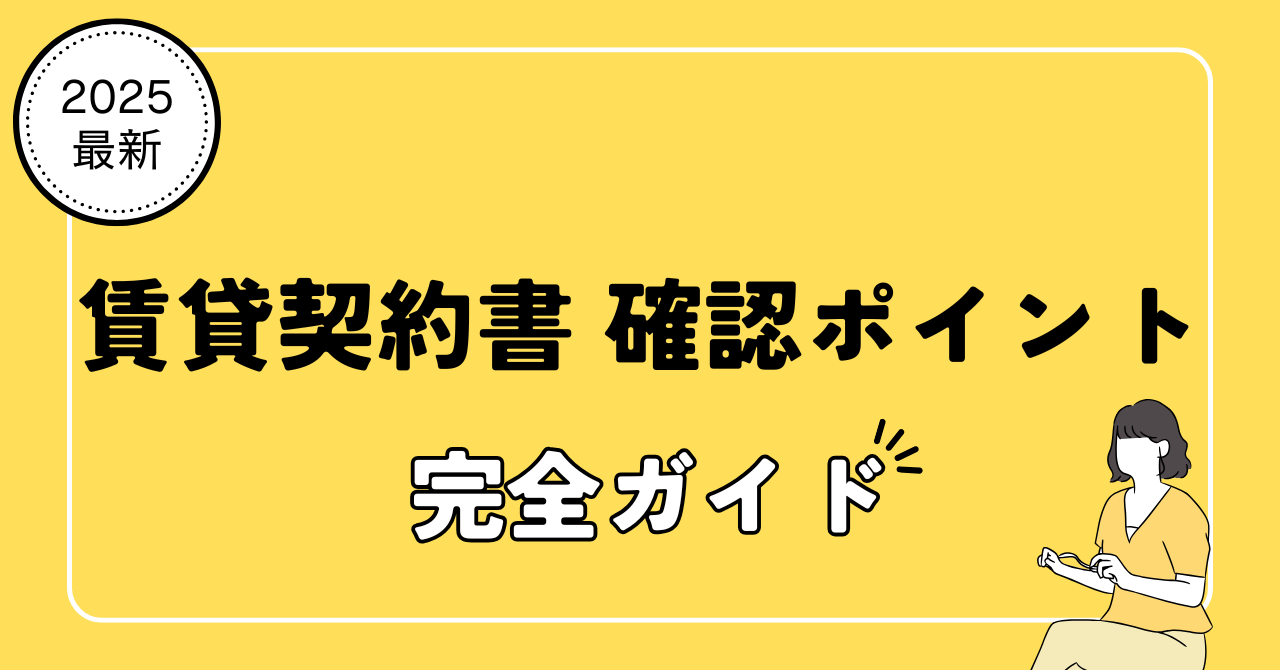賃貸契約書の署名は慎重に行いましょう。一度サインすると後から変更するのは非常に困難です。
特に敷金の返還条件、原状回復の範囲、保証人の責任など、トラブルになりやすい項目は入念にチェックする必要があります。国土交通省の標準契約書や関連法令に基づいて、適正な内容かどうかを確認することが重要です。
この記事では、契約前に必ずチェックすべきポイントから具体的な修正依頼方法まで、賃貸契約書の確認手順を詳しく解説します。
参考: 初期費用の値下げ交渉の完全マニュアル|仲介手数料半額・礼金ゼロの実現方法
参考: 引越し費用の値下げ交渉はできる?成功しやすい交渉方法とテンプレート例文
参考: 物件の選び方完全ガイド|失敗しないための7つのステップ
参考: 【2025年完全版】物件内見の教科書|失敗しない20のチェックリストと危険な物件の見抜き方
契約書署名前に必ずチェックすべき7つの重要項目
賃貸契約書には多くの条項がありますが、特にトラブルになりやすい以下の7項目は必ず確認してください。
| チェック項目 | 重要度 | 確認ポイント | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 重要事項説明書との整合性 | ★★★★★ | 35条書面と37条書面の条件一致 | 宅地建物取引業法 |
| 敷金の返還条件 | ★★★★★ | 返還時期・控除項目の明記 | 民法622条の2 |
| 原状回復の範囲 | ★★★★★ | 通常損耗・経年変化の扱い | 国交省ガイドライン |
| 保証人の責任範囲 | ★★★★☆ | 極度額(上限金額)の明記 | 民法改正(2020年施行) |
| 仲介手数料の妥当性 | ★★★☆☆ | 上限(家賃1.1か月分)の遵守 | 宅地建物取引業法 |
| 禁止・制限事項 | ★★★☆☆ | ペット・楽器・改装等の条件 | 契約の内容 |
| 更新・解約条件 | ★★★★☆ | 更新料・解約予告期間 | 標準契約書準拠 |
重要事項説明書と契約書の突合チェック
契約書にサインする前に、重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)の内容が一致しているか必ず確認しましょう。
宅地建物取引業者は、契約締結前に重要事項説明書(35条書面)で重要事項を説明し、契約締結時に契約書(37条書面)を交付することが義務付けられています。2022年からはIT重説や書面の電子化も可能になりました。
突合すべき主要項目
- 賃料・共益費・支払条件
金額・支払日・振込先等が説明書と契約書で一致しているか - 契約期間・更新条件
契約期間・更新料・更新方法が同じ内容になっているか - 敷金・礼金
金額・返還条件・使途が説明書の内容と一致しているか - 禁止・制限事項
ペット可否・楽器演奏・リフォーム等の条件が同じか
説明書と契約書の内容が異なる場合は、必ず署名前に確認を求めましょう。説明書の内容が優先されるべきですが、契約書の条項が最終的な合意内容となるため、修正が必要です。
敷金返還でトラブルを避けるチェックポイント
敷金に関するトラブルは賃貸契約で最も多い問題です。民法の規定を正しく理解して確認しましょう。
敷金は、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。賃借人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、敷金の返還を請求することができる。
契約書で確認すべき敷金条項
- 敷金の定義
「預かり金」として担保目的であることが明記されているか - 返還時期
「退去・物件返還後」に返還されることが明記されているか - 控除項目
家賃滞納・原状回復費用等の控除項目が具体的に記載されているか - 精算方法
控除額の算定方法・領収書の提示等が明記されているか
原状回復の適正な範囲を確認する
原状回復に関する特約は、国土交通省のガイドラインに基づいて適正かどうか判断できます。
通常の居住使用による損耗・経年変化は貸主負担が原則です。借主負担とする特約を設ける場合は、以下の要件が必要です:
• 特約の必要性があること
• 借主が内容を認識していること
• 借主が特約による修繕等の義務負担の意思表示をしていること
よくあるNG特約とOK特約の例
| 項目 | NG例(要修正) | OK例(適正) |
|---|---|---|
| クリーニング費用 | 「退去時に全額借主負担」 | 「通常清掃を超える汚損は○万円以内で借主負担」 |
| 壁の汚れ | 「壁紙の張替えは借主負担」 | 「故意・過失による汚損・破損は借主負担」 |
| 畳・フローリング | 「全面張替え費用は借主負担」 | 「通常損耗を超える汚損・破損は借主負担」 |
| 設備修繕 | 「設備の修理・交換は全て借主負担」 | 「借主の故意・過失による故障は借主負担」 |
保証人の責任範囲と極度額の確認
2020年の民法改正により、個人根保証契約には極度額(責任の上限額)の設定が必須となりました。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)において、保証人が個人である場合は、極度額を定めなければその効力を生じません。極度額の定めがない保証契約は無効となります。
保証条項で確認すべき内容
- 極度額の明記:「保証人の責任限度額○○万円」等の具体的金額
- 対象債務の明確化:家賃・共益費・原状回復費用等の範囲
- 保証期間:契約期間中のみか、更新後も継続かの明記
- 通知義務:家賃滞納時の保証人への連絡義務
契約書確認の実務フロー
効率的かつ確実に契約書をチェックするための手順をご紹介します。
- 重要事項説明書の受領・確認
IT重説または書面で受領し、不明点を質問 - 契約書ドラフトとの突合
説明書と契約書の条件が一致しているか赤ペンチェック - 法的適正性の確認
敷金・原状回復・保証等が法令・ガイドラインに準拠しているか - 修正依頼(必要に応じて)
問題のある条項の修正をメール等で依頼 - 最終確認・署名
修正内容が反映されていることを確認してから署名
修正依頼のメールテンプレート
問題のある条項を発見した場合の修正依頼テンプレートです。法的根拠を示して丁寧に依頼しましょう。
件名:契約書の修正依頼について(○○マンション○号室) ○○不動産 ご担当者様 いつもお世話になっております。 ○○マンション○号室の契約についてご相談の○○です。 契約書ドラフトを拝見いたしましたが、 以下の点について修正をお願いできればと思います。 ■修正依頼事項 1)敷金返還条項について 現状:「退去時に原状回復費用を差し引いて返還」 希望:「退去・物件返還後に、未払家賃等を控除した残額を返還」 根拠:民法622条の2の規定に準拠 2)原状回復特約について 現状:「壁紙・床材の張替費用は借主負担」 希望:「通常の居住使用による損耗・経年変化を除き、故意・過失による損傷は借主負担」 根拠:国交省原状回復ガイドラインの原則 3)保証人条項について 現状:極度額の記載なし 希望:「保証人の責任限度額:○○万円」の明記 根拠:民法改正(2020年4月施行)により極度額設定が必須 お忙しい中恐縮ですが、上記修正についてご検討いただき、 修正版の契約書をご送付いただけますでしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。 ○○(氏名) 電話:090-0000-0000 メール:example@email.com
よくある問題条項と修正方法
実際の契約書でよく見かける問題のある条項と、適正な修正例をご紹介します。
敷金関連の問題条項
| 問題のある条項 | 何が問題か | 適正な修正例 |
|---|---|---|
| 「敷金は退去時に相殺し、残額があれば返還」 | 返還時期が不明確 | 「退去・物件返還後に、債務控除の残額を返還」 |
| 「クリーニング費用○万円は敷金から控除」 | 金額の根拠が不明 | 「通常清掃を超える汚損があれば実費で控除」 |
| 「敷金は返還しない」 | 民法に反する内容 | 「債務控除後の残額は返還する」 |
原状回復関連の問題条項
| 問題のある条項 | 何が問題か | 適正な修正例 |
|---|---|---|
| 「全室クリーニング費用は借主負担」 | 通常損耗も負担させている | 「故意・過失による汚損のみ借主負担」 |
| 「畳・壁紙は入居年数に関わらず借主負担」 | 経年変化も負担させている | 「通常使用による損耗・経年変化は貸主負担」 |
| 「原状回復費用は敷金の範囲内で全額借主負担」 | 範囲が曖昧で過大 | 「ガイドラインに基づき、借主負担分のみ請求」 |
電子契約と印紙税の確認ポイント
2022年から賃貸契約でも電子契約が可能になりました。電子契約を選択する場合の確認ポイントです。
• 借主の同意があること
• 適切なシステム環境の確保
• 電子署名の仕組みが整備されていること
• 契約書の保存・閲覧方法が明確であること
電子契約のメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 電子契約は印紙税不要 | 紙契約では印紙代が必要 |
| 保存・管理 | データで永続保存可能 | システム障害のリスク |
| 手続きの速さ | 即座に契約完了 | 熟考時間が短くなりがち |
| 修正・変更 | 修正が比較的容易 | 変更履歴の管理が重要 |
署名前の完全チェックリスト
契約書にサインする前に、以下の全項目を確認してください。
【基本情報】
□ 物件の住所・部屋番号が正確か
□ 契約者名・連帯保証人名が正確か
□ 契約期間・開始日が希望通りか
【金銭条件】
□ 家賃・共益費の金額が説明書と一致するか
□ 敷金・礼金の金額と返還条件が明記されているか
□ 更新料・違約金の条件が明確か
□ 仲介手数料が法定上限内か
【権利・義務】
□ 原状回復の範囲が適正か
□ 修繕責任の区分が明確か
□ 禁止・制限事項が受け入れ可能か
□ 保証人の極度額が明記されているか
【解約・更新】
□ 解約予告期間が明記されているか
□ 更新手続きの方法が明確か
□ 契約終了時の手続きが明記されているか
【特約条項】
□ 特約の内容が法的に有効か
□ 特約による負担が過大でないか
□ 特約の根拠が明確か
よくある質問
重要事項説明書と契約書の内容が違う場合はどうすればよいですか?
必ず署名前に確認を求めてください。重要事項説明書で説明された内容と契約書の条項が異なる場合は、契約書の修正が必要です。不明確な部分は必ず質問しましょう。
敷金が返ってこない条項は有効ですか?
民法上、敷金は原則として返還されるべきものです。「敷金は返還しない」という条項は法的に無効となる可能性が高いため、修正を求めましょう。
保証人条項に極度額が記載されていません。どうすべきですか?
2020年の民法改正により、個人根保証契約では極度額の設定が必須です。極度額の記載がない保証契約は無効となるため、必ず金額を明記してもらいましょう。
契約書の特約で過大な負担を求められています。
特約の内容が法令やガイドラインに反している場合、または著しく借主に不利な場合は、修正を求めることができます。国交省のガイドライン等を根拠に相談してみましょう。
電子契約と紙契約、どちらが良いですか?
電子契約は印紙税が不要でコスト面でメリットがありますが、システム障害等のリスクもあります。どちらも法的効力は同じなので、自分にとって管理しやすい方法を選択しましょう。
契約書の修正を依頼したら断られました。
法的根拠のある修正依頼であれば、理由を詳しく聞いてみましょう。それでも修正に応じてもらえない場合は、他の物件を検討することも選択肢です。
まとめ
賃貸契約書の確認は、将来のトラブルを防ぐために欠かせない重要な作業です。特に敷金の返還、原状回復の範囲、保証人の責任については、法的な知識を持って適正性を判断することが大切です。
1. 重要事項説明書との突合:説明内容と契約条件の一致確認
2. 法的根拠の理解:民法・ガイドライン等に基づく適正性判断
3. 署名前の修正依頼:問題のある条項は契約前に修正
4. 将来リスクの評価:更新・解約・トラブル時の対応も考慮
5. 専門用語の理解:不明な用語は必ず質問して確認
契約書は法的に拘束力のある重要な文書です。分からない点は遠慮なく質問し、納得してから署名するようにしましょう。適切な確認により、安心して新生活をスタートできます。