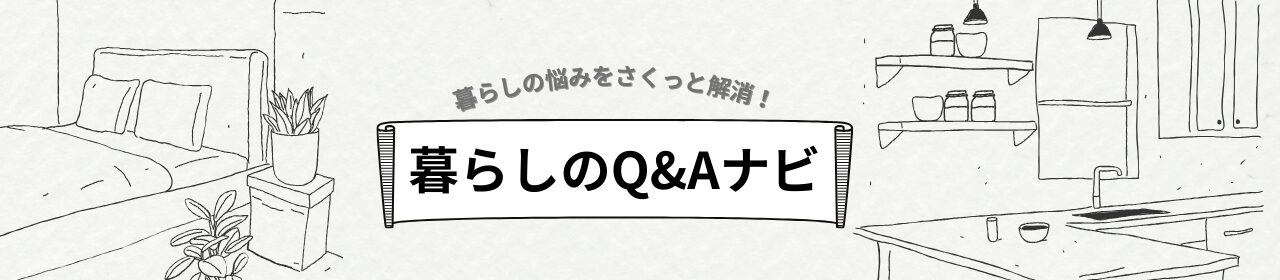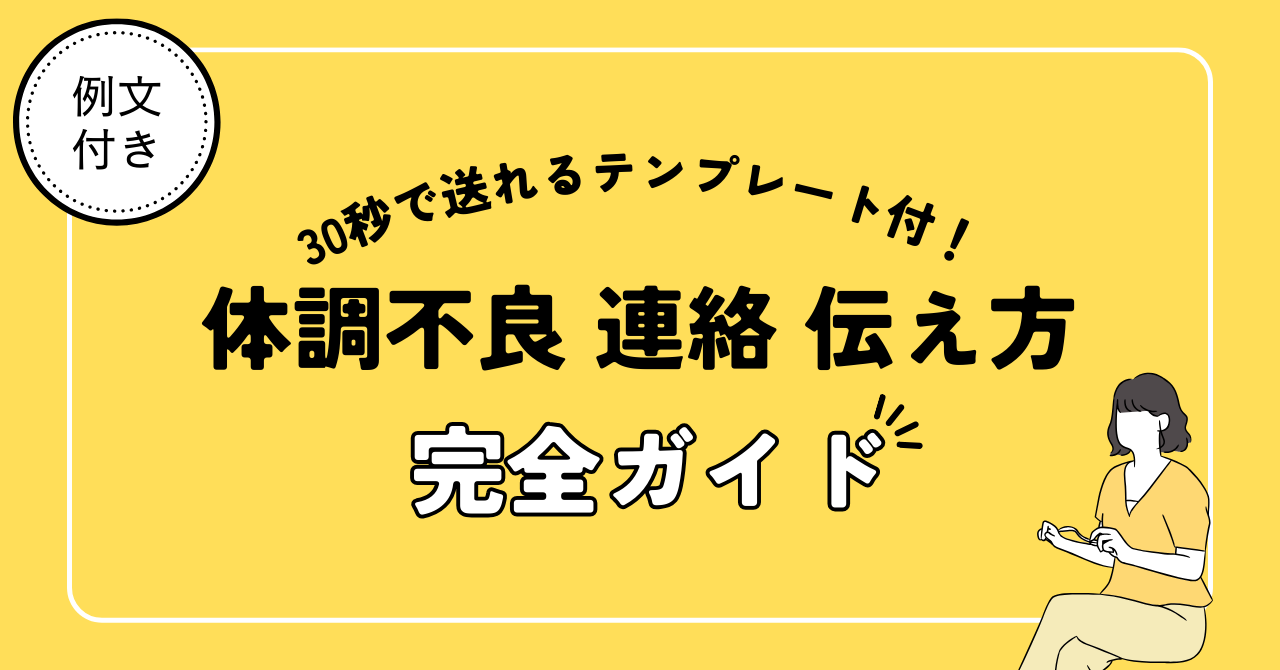朝起きて「発熱で出社できない」「激しい頭痛で仕事に集中できない」そんな体調不良の際、職場への連絡で「どう伝えるべきか」「何を言えばよいか」と悩む方は多いでしょう。適切な連絡方法を知らないと、相手に不安を与えたり、業務に支障をきたしたりする可能性があります。
体調不良の連絡で重要なのは、相手が判断に必要な情報を的確に伝えながら、業務への配慮も示すことです。この記事では、電話・メール・チャットツールごとの適切な連絡方法と、症状別の具体的なテンプレートをご紹介します。
・体調不良連絡の基本マナーと連絡手段の選び方
・上司・同僚・取引先への適切な伝え方
・症状別・状況別のテンプレート例文
・感染症疑いの場合の配慮方法
・復帰時の連絡方法とフォローアップ
参考:遅刻連絡の例文テンプレート|緊急時にすぐ使える電話・メール文例集
参考:目上の人からの「ありがとうございます」への正しい返事は?状況別テンプレートと適切な敬語表現
参考:「断り」の柔らかい言い方ガイド|相手を不快にしない断り方・例文テンプレート
参考:「ご放念ください」の使い方|意味・例文・言い換え表現【ビジネスメール用語】
参考:「とんでもございません」の使い方|基準・例文・言い換え表現【ビジネスメール用語】
参考:『ご確認ください』の言い換え完全ガイド|失礼にしない状況別テンプレート・件名例
参考:『すいません』は不適切?ビジネスで失礼にならない言い換え一覧
参考:敬称の「様」「御中」「各位」の使い分け完全ガイド|迷わない判定方法と例文集
体調不良連絡の基本マナーと連絡手段の選び方
体調不良による欠勤・遅刻・早退の連絡は、適切なタイミングと方法で行うことが重要です。相手の状況を考慮し、最も効果的な連絡手段を選択しましょう。
連絡タイミングの原則
欠勤・遅刻:始業15~20分前までに連絡
早退:症状が現れた時点で可能な限り早く
遅れる理由:「突然の症状」「病院受診の遅れ」などを考慮
注意点:深夜・早朝の個人電話は控える
連絡手段の使い分け
| 連絡先 | 推奨方法 | 理由 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 直属の上司 | 電話(基本) | 緊急性と重要度が高い | 声の調子で体調の深刻さが伝わる |
| 同僚・部下 | メール・チャット | 業務引き継ぎの詳細を記録 | 緊急業務がある場合は電話も併用 |
| 取引先 | 電話+メール | 信頼関係の維持 | 先方の始業時間を考慮 |
| 欠勤2日目以降 | メール可 | 継続的な状況報告 | 回復見込みも併せて報告 |
体調不良連絡の基本構成
効果的な体調不良の連絡は、以下の5つの要素で構成します。この順序を守ることで、相手に必要な情報を漏れなく伝えられます。
- 挨拶と謝罪
「おはようございます」「急な連絡で申し訳ございません」など、基本的な挨拶と謝罪から始めます。 - 症状の簡潔な説明
発熱の度数、主な症状など、勤務可否の判断に必要な事実を1~2文で伝えます。病名の自己診断は避けましょう。 - 対応方針の明示
欠勤、遅刻、早退、在宅勤務への切り替えなど、具体的な対応方針を明確に伝えます。 - 業務への配慮
当日の予定や担当業務について、代行依頼や調整方法を説明します。 - 今後の連絡予定
「明日までに再度連絡します」「受診後に報告します」など、今後の見通しを伝えます。
電話での体調不良連絡テンプレート
電話は最も確実で緊急性を伝えやすい連絡手段です。声の調子からも体調の深刻さが伝わりやすいため、上司への連絡では基本的に電話を使用しましょう。
発熱による欠勤の場合
【電話での伝え方例】 おはようございます。○○です。 急なご連絡で申し訳ございません。 昨夜から38度2分の熱があり、 本日は欠勤させていただきたく存じます。 本日予定していた○○会議については、 △△さんに資料を共有しております。 お客様への連絡は私から入れさせていただきます。 病院を受診後、明日の出社について 改めてご連絡いたします。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 緊急の場合は携帯にご連絡ください。 よろしくお願いいたします。
頭痛による遅刻の場合
【電話での伝え方例】 おはようございます。○○です。 朝から激しい頭痛があり、 10時30分頃の出社予定となります。 9時からの定例会議は 議事録で後ほど確認いたします。 薬を服用して様子を見ておりますが、 症状が改善しない場合は 再度ご連絡いたします。 申し訳ございません。
腹痛・吐き気による早退の場合
【電話での伝え方例】 お疲れさまです。○○です。 腹痛と吐き気がひどく、 このまま業務を続けるのが困難な状況です。 申し訳ございませんが、 本日は早退させていただけますでしょうか。 ○○の件は△△さんに引き継ぎ済みです。 明日の状況については、 夕方までにご連絡いたします。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
メールでの体調不良連絡テンプレート
メールは記録として残り、業務の詳細な引き継ぎ事項を整理して伝えられる利点があります。ただし緊急性が高い場合は電話を優先し、メールは補完的に使用しましょう。
件名の例
- 【緊急】体調不良による欠勤のご連絡(○○)
- 【本日の勤務】体調不良のため遅刻のご連絡(○○)
- 【勤務変更】体調不良による在宅勤務のお願い(○○)
- 【早退】体調不良による早退のご連絡(○○)
基本的なメールテンプレート(欠勤)
件名:【緊急】体調不良による欠勤のご連絡(○○) ○○部長 ○○様 おはようございます。○○です。 急な連絡で申し訳ございません。 昨夜から発熱(38度)と悪寒があり、 本日は欠勤させていただきたく存じます。 【業務への対応】 ・10時からの○○会議:△△さんに資料共有済み ・□□様への提案書:明日提出に延期をお願いします ・○○プロジェクト:緊急対応はございません 【今後の予定】 本日受診予定のため、診察結果と明日の出社について 本日夕方までにご報告いたします。 急な欠勤により皆様にご迷惑をおかけし、 誠に申し訳ございません。 緊急の場合は携帯(090-XXXX-XXXX)にご連絡ください。 何卒よろしくお願いいたします。 ○○ ○○
在宅勤務への切り替え(軽症の場合)
件名:【勤務変更】体調不良による在宅勤務のお願い(○○) ○○課長 ○○様 おはようございます。○○です。 軽い咳と喉の痛みがあり、 周囲への配慮として本日は在宅勤務に 切り替えさせていただけますでしょうか。 【本日の業務予定】 ・○○資料の作成(予定通り実施) ・14時からのお客様との面談(オンラインに変更済み) ・メール・電話対応(通常通り対応可能) 体調に大きな問題はございませんが、 感染予防の観点から在宅での対応とさせていただきます。 ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 ○○ ○○
チャットツールでの連絡テンプレート
Slack・Teams・LINEなどのチャットツールは迅速な連絡に適しています。ただし重要な連絡の見落としを防ぐため、上司への個別連絡も併用することをお勧めします。
上司への個別メッセージ
【Slack/Teams個別メッセージ例】 おはようございます。 体調不良(発熱38度)のため、 本日は欠勤いたします。 詳細はメールでお送りしました。 緊急時はお電話でご連絡ください。 申し訳ございません。
チーム全体への連絡
【チャンネル投稿例】 @channel おはようございます。○○です。 体調不良のため本日は在宅勤務に切り替えます。 対面予定の方には個別にご連絡いたします。 チャット・メールでの連絡は通常通り対応可能です。 ご迷惑をおかけいたします。
症状別・状況別の適切な表現方法
症状を伝える際は、勤務可否の判断に必要な情報を簡潔に伝えることが大切です。過度に詳細な症状説明は避け、客観的な事実を伝えましょう。
| 症状 | 適切な表現例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 発熱 | 「38度の熱があります」「37度8分の発熱により」 | 具体的な体温を伝える |
| 頭痛 | 「激しい頭痛のため」「頭痛がひどく集中できません」 | 業務への影響度を含める |
| 腹痛・嘔吐 | 「腹痛と吐き気があり」「胃腸の調子が悪く」 | 感染性の可能性に配慮 |
| 咳・喉の痛み | 「咳と喉の痛みがあり」「咳が続いており」 | 感染リスクを考慮した対応 |
| めまい・立ちくらみ | 「めまいがひどく」「立ちくらみが続いています」 | 安全面での懸念を伝える |
| 全身倦怠感 | 「体調が優れず」「全身の倦怠感があります」 | 具体的症状があれば併記 |
感染症疑いの場合の配慮と対応
新型コロナウイルス感染症については、2023年5月8日から5類感染症に移行しましたが、職場での感染拡大防止のため適切な配慮が求められます。
厚生労働省のガイドラインでは、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いとされています。特に「発症後5日間かつ症状軽快から24時間経過まで」は外出を控えることが推奨されています。法的な外出自粛義務はありませんが、職場への配慮として重要です。
感染症疑いの場合の連絡例
【感染症疑いの連絡例】 おはようございます。○○です。 発熱(38度)と咳の症状があり、 感染症の可能性も考慮して 本日から数日間、出社を控えさせていただきます。 本日から可能な限り在宅で対応し、 対面予定のお客様には私から 日程変更のご連絡をいたします。 医療機関を受診し、症状の経過を見て 復帰時期をご相談いたします。 皆様にご迷惑をおかけし、 誠に申し訳ございません。
取引先への体調不良連絡テンプレート
取引先との約束がある場合は、信頼関係を維持するため丁寧な対応が必要です。基本的には電話で連絡し、その後メールで改めて謝罪とフォローを行います。
会議・打ち合わせ欠席の電話連絡
【取引先への電話連絡例】 おはようございます。 ○○会社の○○と申します。 本日○時からお約束をいただいておりました ○○の件でご連絡いたします。 申し訳ございませんが、体調不良により 本日の打ち合わせを欠席させていただきたく存じます。 代理で弊社の△△が伺わせていただくか、 お時間が許すようでしたら後日改めて お時間をいただけますでしょうか。 急なご連絡となり、誠に申し訳ございません。
取引先へのお詫びメール
件名:本日の会議欠席のお詫び(○○会社 ○○) ○○株式会社 ○○部 ○○様 いつもお世話になっております。 ○○会社の○○です。 本日○時からお約束をいただいておりました ○○に関する打ち合わせの件でご連絡いたします。 体調不良により急遽欠席させていただくこととなり、 直前のご連絡となりましたこと、深くお詫び申し上げます。 つきましては、改めて下記日程でお時間をいただけますでしょうか。 【候補日程】 ・○月○日(○)14:00~16:00 ・○月○日(○)10:00~12:00 ・○月○日(○)15:00~17:00 ご都合の悪い場合は、○○様のご都合に合わせて 調整させていただきます。 この度は貴重なお時間を頂戴していたにも関わらず、 ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。 引き続きよろしくお願いいたします。 ○○会社 ○○部 ○○ ○○ TEL:000-XXXX-XXXX Email:xxx@example.com
復帰時の連絡とフォローアップ
体調が回復し職場に復帰する際の連絡も、今後の信頼関係に影響します。適切なタイミングと内容で復帰の意思を伝えましょう。
復帰連絡のタイミング
前日夕方まで:翌日復帰予定の連絡
当日朝:体調確認後の最終連絡
復帰初日:出社後の挨拶と感謝
注意点:無理な復帰は再発リスクを考慮
復帰連絡テンプレート
件名:体調回復のご報告と明日からの出社について ○○部長 ○○様 お疲れさまです。○○です。 この度は体調不良でお休みをいただき、 ありがとうございました。 おかげさまで体調が回復いたしましたので、 明日○月○日(○)から通常通り出社いたします。 休業中は○○様をはじめ、 チームの皆様にはご迷惑をおかけいたしました。 明日から気持ちを新たに業務に取り組み、 お休みいただいた分も含めて頑張ります。 引き続きよろしくお願いいたします。 ○○ ○○
復帰初日の挨拶
【復帰初日の挨拶例】 おはようございます。 この度はお休みをいただき、ありがとうございました。 体調も完全に回復し、本日から通常通り 業務に従事いたします。 休業中はご迷惑をおかけいたしましたが、 おかげさまで安心して療養することができました。 改めて、ご配慮いただき感謝申し上げます。 今後ともよろしくお願いいたします。
よくある失敗例と改善方法
体調不良の連絡では、症状の辛さから適切な対応ができないことがあります。以下の失敗例を参考に、相手への配慮を忘れないよう心がけましょう。
| 失敗例 | 問題点 | 改善方法 |
|---|---|---|
| 「体調が悪いので休みます」のみ | 情報不足で状況判断できない | 症状、復帰予定、業務対応を含める |
| 病状の詳細すぎる説明 | 不要な情報で要点が伝わらない | 勤務可否に必要な症状のみ簡潔に |
| 曖昧な表現「なんとなく調子が…」 | 深刻度が伝わらない | 具体的な症状を客観的に説明 |
| 始業時刻を過ぎてからの連絡 | 業務調整が後手になる | 体調不良が判明した時点で即連絡 |
| 業務調整を相手任せ | 相手に負担をかける | 可能な範囲で代案や調整案を提示 |
| 復帰連絡を怠る | 相手を不安にさせる | 定期的な状況報告と復帰予定の明示 |
状況別の対応方法
体調不良の程度や症状に応じて、最適な対応方法を選択することが重要です。それぞれの特徴と適用場面を理解しておきましょう。
| 対応方法 | 適用場面 | 連絡時のポイント |
|---|---|---|
| 欠勤 | 高熱、激しい症状、感染症疑い | 復帰予定の見通しと業務引き継ぎ |
| 遅刻 | 軽い症状、薬で改善見込み | 具体的な到着時刻を明示 |
| 早退 | 勤務中の症状悪化 | 残り業務の引き継ぎを明確に |
| 在宅勤務 | 軽症、感染リスク配慮 | 実施予定業務を具体的に提示 |
よくある質問
電話とメールのどちらで連絡すべきですか?
基本的には電話での連絡が推奨されます。緊急性が伝わりやすく、相手からの質問にもその場で答えられるためです。ただし声が出ない場合や深夜・早朝の場合は、メールやチャットツールで先に連絡し、「後ほど電話いたします」と付け加えると良いでしょう。会社によってはチャットツールやメールでの連絡が一般的になっているところもあるため、事前に社内ルールを確認しておくことをお勧めします。
どの程度詳しく症状を説明すべきですか?
勤務可否の判断に必要な範囲で簡潔に伝えることが重要です。発熱の場合は具体的な体温、その他の症状は業務への影響度を含めて1~2文で説明しましょう。病名の自己診断や詳細な病状説明は避け、「発熱38度」「激しい頭痛」「腹痛と吐き気」など客観的な症状を伝えることが適切です。
軽い咳だけでも休むべきでしょうか?
周囲への感染リスクを考慮して判断することが重要です。軽い咳でも、感染症の可能性がある場合は在宅勤務への切り替えや休暇を検討しましょう。特にお客様対応や会議が多い日は、周囲への配慮として出社を控えることをお勧めします。新型コロナウイルス感染症の5類移行後も、職場での感染拡大防止は重要な配慮事項です。
在宅勤務に切り替える場合の連絡で注意すべき点は?
実施予定の業務内容を具体的に伝えることが重要です。「資料作成」「メール対応」「オンライン会議参加」など、在宅でも継続できる業務を明確にし、対面予定があった場合の調整方法も併せて連絡しましょう。また、体調に問題がないことも併せて伝え、感染予防の観点からの配慮であることを明確にすることが大切です。
体調不良が数日続く場合の連絡頻度は?
毎日の状況報告が基本です。「明日までに再度連絡します」として、翌日の朝に体調と出社予定について連絡しましょう。3日以上続く場合は、医師の診断や診察結果を含めて報告すると、より適切な判断ができます。長期化が予想される場合は、病院の診断書等も準備し、人事部との相談も検討してください。
取引先との約束がある場合はどう対応しますか?
まず電話で欠席を伝え、その後メールで改めて丁寧な謝罪を行います。代理者の派遣が可能か、日程の再調整ができるかを具体的に提案し、相手の都合を最優先に調整しましょう。直前の連絡となってしまったことへのお詫びと、今後の信頼関係維持への配慮を示すことが重要です。
復帰時にはどのような連絡をすべきですか?
前日夕方までに復帰予定を連絡し、当日朝に体調の最終確認を報告します。復帰初日には上司や同僚への感謝の挨拶を忘れずに行いましょう。「体調が完全に回復したこと」「休業中の配慮への感謝」「今後の業務への意欲」を伝えることで、円滑な職場復帰ができます。
体調不良連絡のチェックリスト
連絡前に以下の項目を確認し、必要な情報が揃っているかチェックしましょう。
□ 適切な連絡手段を選択している(電話・メール・チャット)
□ 挨拶と謝罪から始めている
□ 症状を客観的かつ簡潔に説明している
□ 対応方針(欠勤/遅刻/早退/在宅)を明確にしている
□ 当日の業務や予定への対応を示している
□ 復帰予定や今後の連絡について伝えている
□ 感染症疑いの場合は周囲への配慮を示している
□ 緊急連絡先を相手に伝えている
まとめ
体調不良の連絡は、働く上で避けられない場面の一つです。しかし適切な方法で行うことで、相手の理解を得ながら、自分の体調回復に専念することができます。
重要なのは、迅速性・明確性・配慮の3つを兼ね備えた連絡を心がけることです。「挨拶・謝罪→症状→対応方針→業務配慮→今後の連絡」の5つのステップを基本として、状況に応じて適切な連絡手段とテンプレートを活用してください。
また感染症が疑われる場合は、周囲への配慮を最優先に考えることが重要です。自分の体調管理はもちろん、職場全体の健康を守るという責任感を持って行動しましょう。
体調不良は誰にでも起こりうることです。無理をして悪化させるよりも、適切に休息を取って早期回復を目指すことが、結果的に職場全体のためにもなります。この記事のテンプレートを参考に、いざという時に適切な連絡ができるよう準備しておいてください。